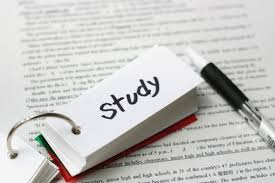2019年5月22日
「外国の公的機関」と「外国の教育機関」について
在留資格の中には、「外国の公的機関」や「外国の教育機関」で一定の研修や教育を受けることで在留資格取得の条件が緩和されるものや、研修や教育を受けることが必須条件となっているものがあります。
では、「外国の公的機関」、「外国の教育機関」とはどういう機関のことでしょうか。以下で説明します。
外国の公的機関
在留資格「研修」は、外国の公的機関で1か月以上かつ 160 時間以上の外部講習を実施した場合には、日本で必要な講習の時間数が緩和されます。
この「外国の公的機関」とは、外国の国又は地方公共団体の機関をいいます。
なお、中国には、国家の公益のため、国家機関又は他の組織が国有資産を利用して設立し、教育、科学、文化、衛生などに関する活動を行い、社会に奉仕する組織である「事業単位法人」がありますが、この事業単位法人は、日本における独立行政法人や公益法人のような組織であるため、「外国の公的機関」には該当しません。
外国の教育機関
日本で演劇などを行うために在留資格「興行」を取得しようとするときは、「外国の教育機関」で2年以上、演劇などを専攻しなければいけない場合があります。
また、外国料理の調理師として在留資格「技能」を取得しようとするときは、原則として10年以上、調理師としての実務経験がなければいけませんが、この「10年以上の経験」には、「外国の教育機関」で調理・食品製造を専攻した期間を含めていいこととされています。
この「外国の教育機関」とは、その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育終了後に入学するものをいいます。
以上が「外国の公的機関」と「外国の教育機関」の説明になります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、在留資格について概要を書いていきます。
2019年5月21日
「学歴」について
日本で働くための在留資格では、学歴や実務経験を条件とされることが多くあります。
今回は、「学歴」について説明します。
在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「特定活動」に 関係する基準省令には、「大学を卒業し」、「これと同等以上の教育を受け」または「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める 要件に該当する場合に限る)」を求める規定があります。
「大学を卒業」とは
学士又は短期大学士以上の学位を取得した人は、「大学を卒業」した人として扱われます。
「これ(=大学を卒業)と同等以上の教育を受ける」とは
以下の人たちは「大学卒業と同等以上の教育」を受けた人として扱われます。
1 大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者
2 航空大学校、防衛大学校など、当該機関の教員が「一般の職員の給与に関する法律」の適用を受ける機関、設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関の卒業者
3 学校教育法施行規則第155 条第 1 項第 4 号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び、これに相当する外国の教育機関の卒業者
4 文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている 機関の卒業者
5 学校教育法第102 条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者
「本邦の専修学校の専門課程を修了」とは
1 「本邦の専修学校」とは、本邦に所在しているものをいいます。
2 「(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)」とは、以下のいずれかの場合です。
(1)①本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、②「専門士」と称することができること。
(2)「高度専門士」と称することができること。
3 専門士・高度専門士とは以下のような要件を満たした人になります。
専門士 高度専門士
修業年限 2年 4年
授業時間数 1700時間以上 3400時間以上
共通 試験等による成績評価及び卒業認定
4 在留資格「研究」の上陸許可基準に適合するためには「高度専門士」の称号が付与されている ことが必要になります。
「従事しようとする業務と専攻科目との関連性」について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学または専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務とが関連していることが求められます。
最近は、日本の大学の卒業者の場合、この関連性が緩やかに判断される傾向にありますが、詳しいことはまた別の機会に書きたいと思います。
以上が「学歴」についての説明になります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、「外国の公的機関と外国の教育機関の範囲」について説明します。
2019年5月20日
外国人が派遣会社で働く場合
日本で「働くための在留資格」を取得する場合には、「申請する人」と「申請する人が働く予定の機関(会社など)」が審査されます。
申請する人が派遣会社(労働者派遣事業を営む企業)で働く場合には、どのような点がチェックされるのでしょうか。
「派遣」について
まずは「派遣」とはどの様な労働形態であるかを紹介していきます。
①労働者派遣の意義
自分の雇用する労働者を、雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させることをいいます。
他人に対し、その労働者を雇用させることを約束している場合は該当しません。
②派遣に関する法的制限
(1) 派遣期間について
・派遣先への派遣期間は原則として1年であり、3年まで延長することが可能ですが、労働者の代表の意見を聴取する義務があります。
・期間は同一業務について通算します。
・期間を超えて同一の業務を継続する場合、派遣労働者を直接雇用しなければなりません。
(2)派遣業務について
・派遣法施行令で定められた、専門的な知識や技術を要する18業務
・業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
・事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務で、一定の期間内に完了することが予定されているもの
・その業務が1か月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数と比較して相当程度少なく、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
・派遣先に雇用される労働者が労働基準法の規定により休業し、育児休業、介護休業等育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業をする場合の労働者の業務、その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める労働者の業務
・派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する介護休業をし、これに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合の労働者の業務
医療業務(ただし、紹介予定派遣、出産・育児・介護休業の代替要員、僻地及び社 会福祉施設への派遣は可能。)、建設業務、警備業務、港湾業務に労働者を派遣することはできません(特に、警備はそれ自体が派遣同等となります。)。
(3)再派遣の禁止
派遣社員を派遣先から更に派遣させることはできません。
③派遣労働者の分類
2つの派遣労働者の分類について説明します。
(1) 常用型派遣
派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が結ばれている状態の派遣の事をいいます。
「正社員派遣」、「定常型派遣」とも呼ばれています。
常用型派遣労働者には、特定労働者派遣事業主に正社員や契約社員として雇用される労働者や雇用主が一般労働者派遣事業主であっても、正社員や契約社員として雇用されている労働者があります。
(2) 登録型派遣
派遣先が存在する時のみに派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣をいいます。
④労働者派遣事業とは
(1) 特定労働者派遣事業
派遣元に常時雇用される労働者を他社に派遣する形態を指します。
一般労働者派遣の業者に比べると、特定の事業所に対し技術者などを派遣する業者が多いのが特徴です。
(2) 一般労働者派遣事業
派遣元に常時雇用されない労働者(契約社員)を他社に派遣する形態をいいます。
臨時 ・日雇い派遣もこれに該当します。
一般的に「派遣会社」にこの形態の事業者が多いです。
派遣会社で働く場合の審査
申請する人が派遣会社で働く場合、チェックは以下のように行われます。
①活動内容
申請する人が行おうとする活動は、派遣先において従事しようとする活動に基づいて判断されます。
②活動の継続性
派遣労働者には、上記のとおり常用型派遣と登録型派遣があります。
「活動が継続的」であると判断されるには、原則として常用型派遣であることが必要です。
ただし、登録型派遣であっても、許可する在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において許可する在留資格に関する活動を行うことが見込まれる場合は、「活動が継続的」であると判断される場合もあります。
③機関の規模
「働くための在留資格」では、働く機関の規模などに応じて提出資料が変わります。
派遣労働者の場合は、雇用契約を締結している機関(≒派遣元)に応じた資料を提出する必要があります。
以上が外国人が派遣会社で働く場合の説明になります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、在留資格に関わる「学歴」について説明します。
2019年5月17日
「常勤の職員」について
「経営・管理」、「興行」、「留学」、「研修」などの在留資格には、申請をする人が経営する予定の会社や、所属する予定の機関(会社・学校など)に、「常勤の職員」がいる必要がある場合があります。
一例として、「留学」の場合であれば、申請をする人が中学校や小学校に入学する予定の場合、その中学校や小学校には、「外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する『常勤の職員』」がいる必要があります。
「常勤の職員」とは??
「常勤の職員」とは、常に勤務している職員ということですが、以下のような基準で判断されます。
①勤務が、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その職務に従事しなければならないものであること。
②職務に応じた給与等が設定されていること。
③労働日数が週5日以上、かつ、年間 217 日以上であって、かつ、週労働時間が 30 時間以上であること。
④入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員 に対し 10 日以上の年次有給休暇を与えられること。
⑤雇用保険の被保険者となっていること。
「常勤の職員」に当たらない場合
使用者と労働者との間で締結される契約の形態については、直接雇用のほかに「出向」、「派遣」及び「請負」の形態がありますが、「出向」のうちの「在籍出向」、 「派遣」と「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所 の「常勤の職員」には当たりません。
以下で詳しく説明します。
「出向」について
「出向」とは、労働者が自己の使用者を離れて第三者の下で就労する労働形態をいいます。
「出向」には、労働契約上の契約当事者たる地位(従業員としての地位)を出向元会社に残す場合の「在籍出向」と、労働契約上の契約当事者たる地位(従業員としての地位) を出向先会社に移す場合の「移籍出向」があります。
労働者が出向する場合の元々雇用されている企業を「出向元」と呼び、出向により新たに勤務することとなる企業を「出向先」と呼びます。
「在籍出向」について
「在籍出向」の場合、出向労働者は、出向元と出向先、双方と労働契約関係を有するが、契約上の権利義務が重複するのではなく、単一である労働契約が内容的に二つに割れて、それぞれの契約に属していることになります。
労働契約内容の分担は、契約の内容により様々ではありますが、退職や解雇に関する事項 については、基本的には出向元が労働契約の当事者となります。
このため、出向先の下で働く出向元からの在籍出向の労働者を、出向先の「常勤の職員」とすることは不適切になります。
「移籍出向」について
「移籍出向」の場合、出向元との労働契約を解消して出向先との間に労働契約を成立させるもので、従業員としての地位が出向先に移転し、一般的に復帰は予定されていないことから、労働者の合意はあくまでも個別的な同意があって認められています。
労働者は、出向先との間に一般的、包括的な労働契約関係をもつこととなるため、 出向先の「常勤の職員」ということになります。
「派遣」について
派遣とは、派遣元の事業主が労働者との雇用契約を維持したままで派遣先の事業主の指揮命令下で労働させるもので、派遣先の事業主と労働者との間に雇用関係が存在しないものをいいます。
この場合、労働者は、出向先との間に一切の雇用関係がない為、労働者は出向先の「常勤の職員」にはなりません。
「請負」
請負については、労働者派遣の場合よりもさらに派遣先と労働者との契約関係は希薄になることから、労働者を派遣先の「常勤の職員」とすることは不適切になります。
しかし、例外的に、企業間の1年以上継続した請負契約に基づき、工事の一部又は全部を請け負った 企業に6か月以上継続的にフルタイムで雇用されるような人については、常勤職員とみなされる場合があります。これは、建設業・造船業に多く見られる請負契約の重層的な産業構造等の特殊性によるものです。
以上が「常勤の職員」についての説明になります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、外国人が派遣事業を営む企業に就職する場合について説明します。
2019年5月16日
在留資格該当性「報酬」について
ここでは、在留資格該当性における「報酬」や、「収入を伴う事業を運営する活動」、「報酬を受ける活動」などについて説明していきます。
前回のブログで説明したとおり、在留資格には、それぞれ「在留資格該当性」というものがあり、在留資格を取得するための条件がいくつかあります。
「報酬」も、その条件に大きく関わってきます。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が条件となる在留資格
在留資格のうち、「経営・管理」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「介護」に関連する基準省令では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という規定があります。2019年4月の入管法改正によって創設された在留資格「特定技能」に関しても同様です。
また、在留資格「興行」に関連する基準省令では、月額20 万円以上の報酬を要件とする規定があります。
「報酬」について
報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいいます。「報酬」には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償など(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
報酬の月額は、賞与等を含めて1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12 分の1で計算されます。
「日本人~と同等額以上」とは、報酬額を基準として一律に判断するのではなく、個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されることになります。
この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考に判断されます。
次に、「収入を伴う事業を運営する活動」「報酬を受ける活動」について説明します。
「短期滞在」など、「収入を伴う事業を運営する活動」、「報酬を受ける活動」を行ってはいけない在留資格があります。そこで、それらの活動の定義が問題となります。
「収入を伴う事業を運営する活動」「報酬を受ける活動」について
役務提供が本邦内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が本邦内にあるか、また、本邦内で支給するかにかかわらず、「報酬を受ける活動」となります。
ただし、本邦外で行われる主な業務に関連して、それに付帯する業務活動を短期間本邦内で行う場合(例えば、日本へ輸出販売した機械の設置、メンテナンスなどのアフターサービスを行うために短期間滞在する場合、本邦内で行われる関連会社間の会議等のために短期間滞在する場合など)に、本邦外の機関が支給する対価は含まれません。
「収入を伴う事業を運営する活動」についての解釈も、「報酬を受ける活動」と同様に、金銭の授受を伴う事業活動の運営を本邦内において行っている場合は該当します。
ただし、本邦外で従事する業務が主な活動の者が、特別な事情により本邦内でそれに属する活動に短期間従事する場合(例えば、本邦内に子会社のある外資系企業の親会社の取締役が、当該子会社の無報酬の代表取締役を兼ねている場合において、主として当該親会社で勤務しているが、大きな商談の締結のために本邦に短期間滞在する場合など)については該当しません。
「短期間」については、単に1回の滞在期間が短期間であっても、中長期的にみて本邦に滞在する期間が相当程度の割合がある場合には該当しません。
以上が「報酬」についての説明になります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、「常勤の職員」について説明します。
2019年5月15日
在留資格該当性「本邦の公私の機関との契約」について
ここでは、「本邦の公私の機関との契約」について説明していきます。
在留資格該当性とは
2019年5月現在、日本では、外国人に対して29の在留資格を認めています。
在留資格を取得するための申請をする外国人は、この29の在留資格に定められている「活動」もしくは「身分又は地位」にあてはまるかどうかを「在留資格該当性」として審査されます。
「就労ビザ」について
日本には、包括的な「就労ビザ」という形の在留資格はありません。
日本で働くための在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「高度専門職」、「研究」、「介護」などいくつかありますが、これらの在留資格に関する「在留資格該当性」として、いくつかの条件があります。
その条件の中の大きな一つが「本邦の公私の機関との契約」、つまり①本邦(=日本)で働く機関が決まっていること。そして②その機関と契約していることです。
「本邦の公私の機関」とは?
国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はない。)が該当します。
また、 本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)外国の法人等、更に、個人であっても本邦で事務所、事業所等を有する場合も含まれます。
「本邦の公私の機関との契約」とは?
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。
ですが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものである必要があります。
特定の機関との継続的契約でない場合は、個人事業主として「経営・管理」に該当する場合があります。
また、「契約」の当事者となることができるのは、自然人や法人格を有する団体に限られています。
例えば、形式上は株式会社の支店等の長が契約書に署名していたとしても、当該支店等の長が当該法人(株式会社)を代理(又は代表)している場合には、法人が契約の当事者であることに注意しなければなりません。
因みに、個人経営の場合には、当該経営者が契約当事者となります。
契約は、本邦において適法に行われるものでなければなりません。
また、在留活動が継続して行われることが見込まれることが条件となります。
「労働契約」について
労働契約の締結については、使用者は、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととなっており、(労働基準法第15条第1項)、 労働契約には、雇用契約のほか、委任契約や請負も含まれます。
外国の公私の機関と本邦の公私の機関とが契約当事者となっている場合
労働契約書において外国の公私の機関と本邦の公私の機関とが外形上の契約当事者となっている場合であっても、以下の⑴から⑹の事項が確認されたときは、「外国人本人と本邦の公私の機関との間に労働契約が成立している」と認められ、「本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行う」という要件を満たすものとして扱われます。
(1) 我が国に入国する者として当該外国人が特定されていること。
(2) 当該外国人の使用者にあたる、本邦の公私の機関が特定されていること。
(3) 本邦の公私の機関が当該外国人と「労働契約を締結する」旨を明示されていること。
(4) 当該外国人の労働条件として、労働基準法施行規則第5条第1項第1号から4号に定める事項が明示されていること。
(5) 本邦の公私の機関が我が国の労働基準法を遵守する旨が明示されていること。
(6) 本邦の公私の機関が当該外国人に対し賃金を直接支払う旨が明示されていること。
以上が在留資格該当性の「本邦の公私の機関との契約」についての説明です。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
次回は、在留資格該当性の「報酬」について説明していきます。